こんにちは。
アロマ大好き看護師の加々美です。
本日は石けんのお話をしたいと思います
日常生活の中で何かとお世話になっている石けん。
体を洗ったり、衣服を洗ったり、掃除に使ったり、必ず自宅にある洗浄剤。今でこそ当たり前のように使っていますが、そもそもどのようにして生まれたのでしょうか?
古代では人は水洗いや灰汁、植物で洗濯をしていました。
遡ること、紀元前3000年。シュメール(現在のイラク)の記録粘土板にすでに薬用としての石けんが登場していたようです。
古代ローマでは羊を焼いて神にお供えをする習慣のあったサポーの丘では滴り落ちた羊の脂と灰が雨に流され、それが川に蓄積して土の中に自然に石けんらしきものができたとか。
当時の人々は不思議な土は汚れをよく落としてくれて、洗濯物がきれいに仕上がると喜んだのが目に浮かびますね。
そうしてサポーの丘に由来し、Soap➡ソープ=石けん
現在の石けんの由来になったと言われています。
上記は日本石鹸洗剤工業会のホームページより。
日本ではどうだったのかというと、
かつての日本は洗濯にむくろじの果皮やさいかちのさや、灰汁が使われていました。
戦国時代末期にポルトガル船によって石鹸がもたらされましたが、とても貴重で将軍や大名などの限られた人たちにしか手に出来ないほど。
なので庶民は植物や灰汁を使って洗濯をし、小豆や大豆の粉に綱領を入れた洗い粉、ヘチマ、ぬか袋、軽石で体を洗っていました。
こうして書いていると、羊を焼いた油に灰が雨と混ざる…とは今の石鹸と比較すると獣臭かっただろうと思います。
灰は金属元素が酸素と結合し固体となったもの。
水に溶かすと強いアルカリ性を示します。
灰のアルカリ性によって動物の脂肪が加水分解され石けんができたという奇跡の産物。
最初は動物の獣臭があったけど、驚きの洗浄力があったため使っていた。しかも最初は土に堆積したものなので、柔らかめの石けんが出来上がっていた。
かつての石けんの課題は、
・獣臭
・柔らかすぎる
だったのでしょう。
12世紀ごろ、地中海沿岸のオリーブ油と海藻灰を原料とした固い石けんが誕生。
この頃石けん産業が盛んだったのはフランスのマルセイユやイタリアのサボナ、ベネチアなど。
サボナという地名がサボンの語源とも言われているようです。
17世紀にはマルセイユが石鹸工業の中心地になり、今のマルセイユ石鹼の由来にもなっています。
18世紀になって、アルカリの需要が増えて海藻や木から灰を作るだけでは追いつかなくなります。
1791年 フランス人科学者のルブランがアルカリ剤の合成に成功します。海水から採った食塩から硫酸ソーダを作り、石灰石と石炭を混ぜて加熱して炭酸ソーダを作り出すもの。
こうして石鹼を大規模に生産することが可能になり、1861年にはベルギーのソルベーによってアンモニアソーダ法が発明されました。これは食塩水にアンモニアガスと炭酸ガスを吹き込んで重炭酸ソーダを作る方法で、ルブランが考案した方法よりも低コストで質の高いソーダが大量に作れました。
その後1890年には食塩水を電気分解してソーダを作る電解ソーダ法がドイツで工業化され、現在では世界の主流になっていて、苛性ソーダを作る手法になっています。
苛性ソーダとは水酸化ナトリウムのこと。
小学生時代に水酸化ナトリウム水溶液を使って、リトマス試験紙を…なんて実験をやったのを思い出しましたが。強アルカリなのは納得。
普段から固形石鹸を使って顔や体を洗ってきて、石けんを作れると知って「私好みに作りたい」と強く思って感動したのを今でも思ってます。
実際にコールドプロセス法にて石けんを作っていますが、作ってすぐに使えないことが悲しくてしょうがない。
このコールドプロセス法というのは、
石鹸製造方法のことを指します。油脂とアルカリを加熱せずに反応熱だけを利用してゆっくり熟成させる製法のこと。
実際に作る過程で、精製水に苛性ソーダを入れて混ぜるとみるみるうちに熱くなります。
実際にその温度を測定したわけではありませんが、作成中に容器ごしに熱湯を触っているかのような温度帯だと感じました。
苛性ソーダを冷まし、植物油を湯煎し温め40℃ぐらいの温度帯で作成することで熱による成分のダメージを最小限にできます。
何と言っても、コールドプロセスの利点は天然のグリセリンがせっけんに残ること。
グリセリンは保湿成分であり、コールドプロセスで作成する中でけん化反応で生まれる産物。
実際ここ半年以上コールドプロセス法で作成した石けんで顔や体を洗っていますが、洗い上がりのツッパリ感が少ないと感じています。
もしかしたら、グリセリンのおかげなのかもしれません。
現代の石鹸製造方法はいくつかあって、
コールドプロセス法のほかに
・中和法
・釜焚きけん化法
・焚き込み法
などがあります。
中和法は、あらかじめ油脂を分解して得られた脂肪酸だけをアルカリを反応させます。なので、短時間であっという間に石鹼が作れます。なので、大手メーカーはこの方法を取り入れ大量生産することが可能になっています。
釜焚きけん化法は、釜に入れた油脂とアルカリ剤を撹拌しながら加熱しけん化反応を起こして石鹸を作る手法。伝統的な石鹸製造法。
焚き込み法は釜焚きけん化法の中でけん化反応が終わった後に塩析をしない方法のこと。塩析とは塩水で石鹸の元を洗うことで不純物を取り除き純度の高い石鹸を得る方法のことで、小規模・家庭や地域で作られる廃油石鹸はこの方法が多め。また液体石鹼はこの手法で作られることが多いようです。
どの手法にもメリット・デメリットがあり、ご自身で調べて納得した石鹸を選び、使用していくことが大事なのだと感じました。
私はコールドプロセス法の石けんを選び、生活の中で役立てていますが、今のところ不便と感じたことはありません。
強いて言えば、4週間の乾燥期間が「早く石けん使いたい…!!!」という気持ちを掻き立て、待ち遠しくなるところでしょうか。
先日オルトケイ酸ナトリウムを使用した廃油石鹸を作成しましたが、皿洗いに使用して特に皮膚トラブルはありません。
また以前は石けん素地を使って手ごね石けんを作り、体を洗うのに使用しましたが、とても使い心地がよかったです。
石けんのことを知れば知るほど面白くて、もっともっと学んでみたくなります。
これからもより一層、アロマやハーブ、石けんの沼にはまりそうです。
※所々私の個人の感想がありますので、ご自身の目で確かめ、情報を養い、石けんを選んでいってもらえたらと思います。

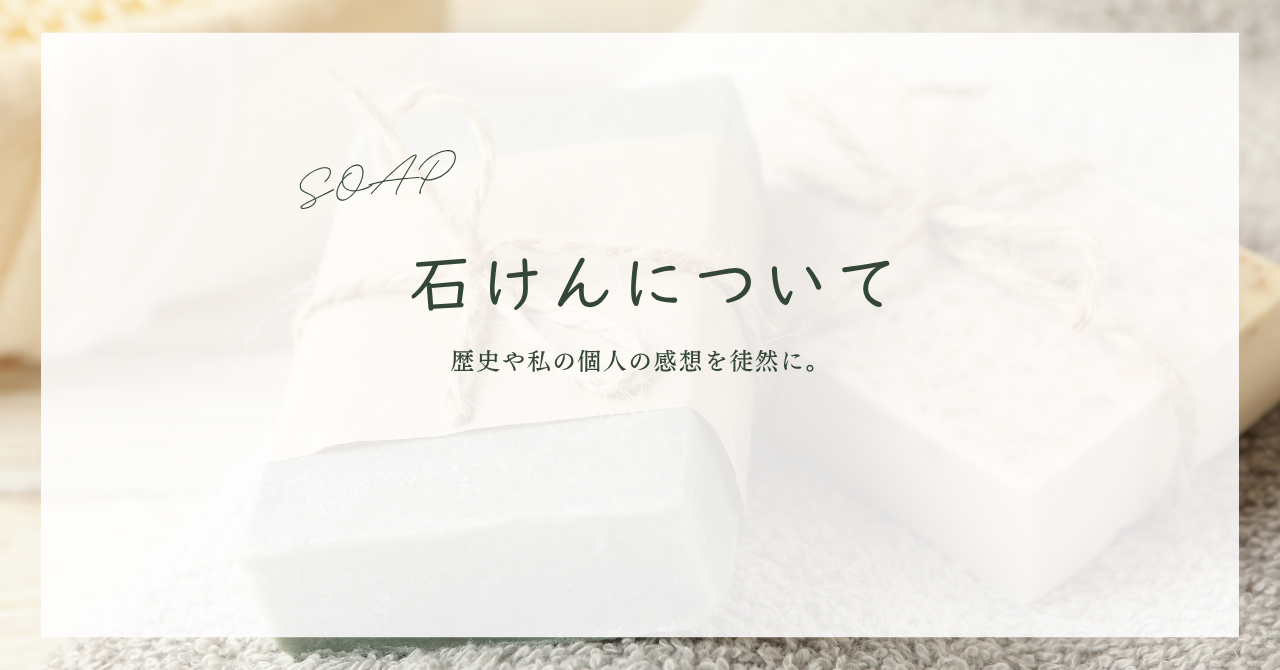
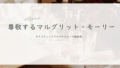

コメント